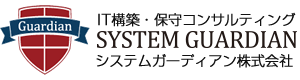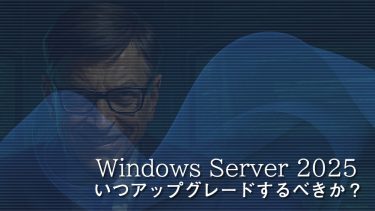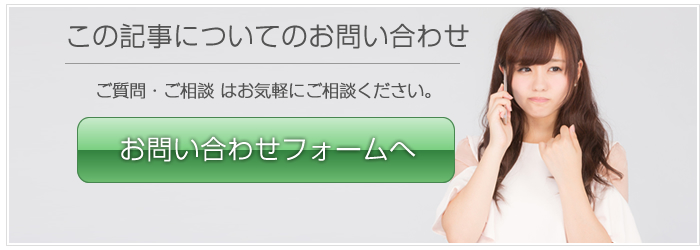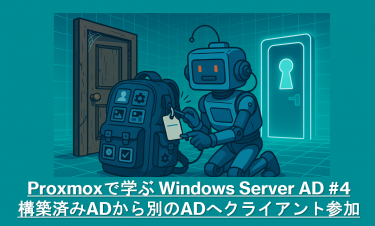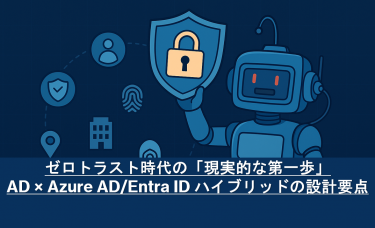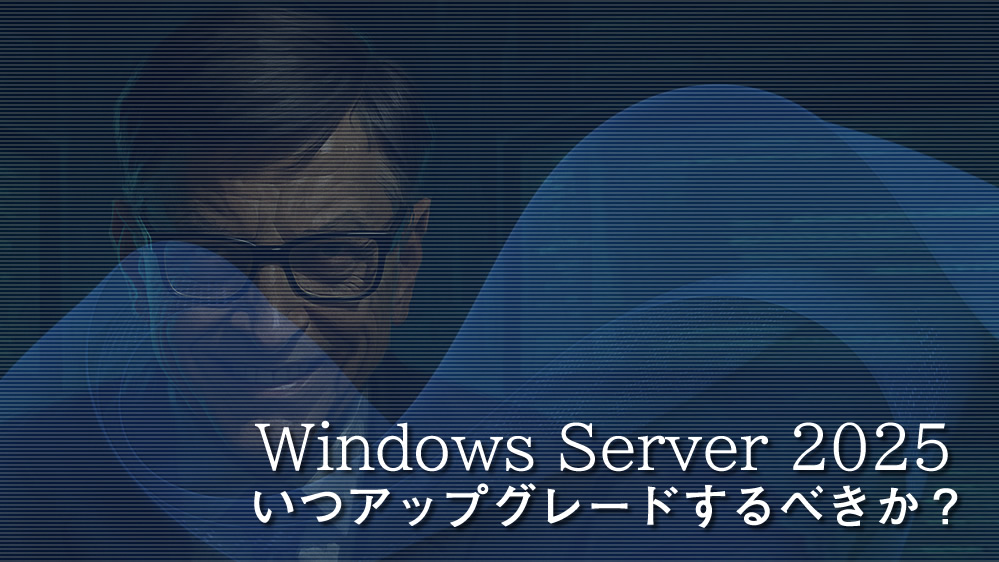
こんにちは、カトーです。
弊社はインフラ専門なので、多くのサーバーを構築・管理・保守していますが、悩ましい問題のひとつに「Windows Server 2025 にいつアップグレードすべきか?」というテーマがあります。
この記事を読んでいるあなたも、それが気になって見ているのではないでしょうか。
――これがマインドスキャンテクノロジーです。
さて、冗談はさておき、昨今の Windows Server はサードパーティ製のアプリやクラウド系の認証との連携などがあるため、単純にアップグレードできないのが現実です。そこで今回は2025年9月現在で「どうすればいいのか」「いつアップグレードすべきか」という指針について考察してみます。
記録として残しておきますので、多くのインフラエンジニアが救われますように。
う、ウィンドウズ万歳……ウィンドウズ万歳……ウィンドウズ万歳……うっぅ
概ね6~7年がアップグレードタイミング
2025年9月1日時点、大前提として、サーバーのアップデートは「購入から6~7年」が目安です。なぜ5年でなく6年から7年なのか?それは一般的にサーバーやネットワーク機器などのハードウェア製品では、購入から5~7年程度の保守期間が設定されており、LTSCやらサポートがあるからです。もちろん予算あまりまくりで、毎年やらOS出たら毎回交換というのもいいですが、現実問題ということでご理解ください。
Windows Server の主なリリース
これまでの主なリリースを振り返ると:
-
NT Server 4.0(1996年)
-
Windows 2000 Server(2000年)
-
Windows Server 2003(2003年)
-
Windows Server 2008(2008年)
-
Windows Server 2008 R2(2009年)
-
Windows Server 2012(2012年)
-
Windows Server 2012 R2(2013年)
-
Windows Server 2016(2016年)
-
Windows Server 2019(2018年)
-
Windows Server 2022(2021年)
-
そして最新の Windows Server 2025(2024年)
こうした流れを見ても分かるように、サーバー OS は2~3年おきに新しいバージョンが登場してきました。
そして、Windows Server のライフサイクルは「長期サービスチャネル(LTSC)」が中心で、通常 2~3 年ごとに新バージョンが登場します。サポート終了日を過ぎた OS を使い続けることはセキュリティリスクを高めるため推奨されませんし、メーカー保守も 5 年を超えると終了したり、交換を促されたりするのが一般的です。そのためメーカー保守が切れると、外部保守ベンダーによる対応やコールドスタンバイ機器の確保が必要になります。つまり「じゃあ、5年じゃないのか?」と思われるかもしれませんが、そこが LTSC のポイントです。
長期サービスチャネル(LTSC)とは何かというと、Windows Server や Windows 10/11 Enterprise で採用されている提供モデルのひとつで、「機能は大きく変えずに、長期間サポートを保証します」という仕組みです。具体的には、LTSC 版の Windows Server は大体 2~3 年ごとに新バージョンが出ますが、1つのバージョンに対して 10 年前後(5 年のメインストリームサポート+5 年の延長サポート)が提供されます。つまり、一度導入すれば長期間安定して運用できるのがメリットです。一方で、かつて存在した「半年チャネル(SAC:Semi-Annual Channel)」は、新機能を頻繁に取り込むモデルでしたが短命に終わり、今は廃止されています。サーバーの世界では「安定して長く使えること」が最優先されるため、結局 LTSC が主流になったというわけです。
つまり、理屈の上では 10 年が最大運用期間ですが、実際にはアプリや周辺機器との調整に半年~1年かかることも多く、さらにハードウェア自体の寿命(5~7年)を考慮すると、そのタイミングで入れ替えるケースが現実的ということです。また、サーバーは数十万円から数百万円する投資であり、企業にとっては経営に直結します。そのため、そう簡単には変更できません。過去には、制御用のシーケンサに直結したサーバーを導入していたお客様がいましたが、制御機器自体が数億円規模だったため、このサーバーもシステム全体と合わせて 15 年以上動かし続ける、ということがありました。つまり、高額な制御機器や基幹システムに依存する環境では、Windows Server のライフサイクルよりも設備投資サイクルが優先されることもある、という実例です。
Windows Server の主なリリース
LTSC を考えると、理屈の上では 10 年運用可能ですが、実際にはアプリや周辺機器の調整に半年~1年かかりますし、ハードウェア自体の寿命(5~7年)も無視できません。そのため、現実的には「ハードの更新タイミングに合わせて OS もアップデートする」ケースが多いのです。実際の現場事例としてたとえば Windows Server 2008 / 2008 R2 からの移行では、多くのお客様が「業務アプリが対応していない」という理由で移行を後回しにしていました。
しかしサポート終了が迫ると、一斉に Windows Server 2012 R2 や 2016 への移行が必要となり、半年以上にわたって検証や調整を行う大規模プロジェクトに発展した例もあります。
中には「どうしても 2008 R2 を残さざるを得ない業務システムがある」という理由で、仮想環境に隔離して一部だけ延命させる暫定対応を取った現場もありました。
こうしたケースを見ると、Windows Server の移行は単なる OS の入れ替えではなく、業務システム全体の棚卸しのタイミング になることが多いのです。特殊なケースとして、サーバーは数十万円から数百万円する投資であり、企業の経営に直結するため簡単には更新できません。過去には、制御用シーケンサに直結したサーバーを導入していたお客様がおり、制御機器自体が数億円規模だったため、このサーバーもシステム全体に合わせて 15年以上動かし続けることになった、という例もありました。こうした場合は、Windows Server のライフサイクルよりも、設備投資サイクルのほうが優先されるのです。
一般企業が取るべき現実的な判断ポイント
-
ハードウェアの寿命に合わせる
サーバー機器の保守は通常5~7年で切れます。メーカー保守が終了すると部品交換や修理が難しくなるため、このタイミングで入れ替えを検討するのが現実的です。 -
OSのサポート期限を逆算する
Windows Server は LTSC で10年サポートされますが、セキュリティ更新が止まった OS を使い続けるのはリスクが大きすぎます。サポート終了日の1~2年前には、次の移行計画を立てておくのが安全です。 -
業務アプリや周辺機器との互換性を確認する
実際の移行で一番時間がかかるのは OS そのものよりも、アプリや業務システムとの動作検証です。特に古い業務アプリが「そのバージョンにしか対応していない」という場合もあるため、早めに棚卸しして、代替策や仮想環境での延命プランを検討しておく必要があります。
ケースバイケースで考える Windows Server 2025 へのアップグレード
最後に、Windows Server 2025 へのアップグレードを考えるときに押さえておきたいポイントです。
-
新規導入やリプレース予定のある企業
これから新しいサーバーを導入するのであれば、最新の Windows Server 2025 を選ぶのが自然です。サポート期間が最も長く、長期的な安定運用が見込めます。 -
Windows Server 2016 / 2019 を利用中の企業
まだサポートが残っているため、急いで 2025 に移行する必要はありません。ただし、ハード更新のタイミングや業務アプリの対応状況を見ながら、数年以内の計画に組み込むと安心です。 -
Windows Server 2012 / 2012 R2 を利用中の企業
すでにサポートが終了しているため、早急に移行が必要です。2025 への直接移行を視野に入れ、アプリや周辺機器の互換性検証を進めるべき段階です。 -
特殊システムを抱える企業
制御機器や業務専用システムが絡む場合は、すぐに移行できないこともあります。その場合は、仮想環境での延命や限定的な利用など、リスクを抑える運用も合わせて検討する必要があります。
つまり「最新だから導入すべき」ではなく、ハードの更新サイクル・OSサポート期限・業務システムの依存関係を天秤にかけて判断するのが、Windows Server 2025 への現実的な向き合い方と言えるでしょう。
SGカトー的な結論
あくまで個人の意見として、結局のところWindows Server のアップグレード時期は「ハードの寿命」「OS のライフサイクル」「業務システムの互換性」の三本柱で決まります。理屈の上では 10 年サポートされる LTSC ですが、実際の現場ではアプリの対応や周辺機器の老朽化を待っていると手遅れになることも少なくありません。メーカー保守が切れる5年を過ぎてから慌てると、計画も検証も追いつかず、結果的にトラブルや追加コストが増えるリスクが高まります。そこで、私からの現実的な提案はシンプルです。
サーバーは6年を目安に交換する。
6年目であれば、まだメーカー保守が続いているケースも多く、交換時期を6年だとすれば、前年度の5年目でメーカーから案内が来た時点で予算をもって、次の移行計画に余裕をもって取り組めます。
また、アプリや周辺機器の対応を検証する時間も確保でき、トラブルを最小限に抑えられるのです。「壊れてから考える」のではなく「余裕を持って計画的に入れ替える」
――これが、長年サーバー運用に関わってきた私、SGカトー的な結論です。
意外と多いのは、ストレージが1台が壊れたor メモリ、もしくは再起動時に特殊ファン壊れて自動起動せずにデータセンター巡業、あぁ..こりゃ、クラウド移行しよう病が発病しがちです。
サーバーを6年で入れ替えることには、コスト・リスク・運用効率の観点から明確なメリットがあります。それはまずコスト面では、メーカー保守が切れる前に入れ替えることで、突発的な故障対応や高額な延長保守契約を避けられます。さらに、計画的なリプレースであれば、予算化もしやすく、中期経営計画に組み込みやすいという利点もあります。次にリスク面です。古い OS を使い続ければ、セキュリティパッチが提供されない状態で運用することになり、情報漏洩やシステム停止のリスクが跳ね上がります。6年交換であれば、まだ余裕を持って安全に次世代 OS に移行できるため、リスクを最小限にできます。最後に運用効率です。ハードウェアの性能は年々向上しており、最新世代のサーバーでは、電力効率や仮想化性能も大幅に改善されています。古いサーバーを無理に延命させるより、6年ごとに更新したほうが結果的に運用コスト削減にもつながります。つまり、6年交換は「安全性を担保しつつ、コストと効率を両立できる最適なタイミング」なのです。
まぁ、そうはいってもインフラって予算直撃するので、社内の立場は難しいのが現実ですよね……
ご相談は無料ですので、ぜひ世間話的にご相談ください。